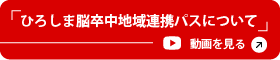第57回備後地域連携を考える会を開催しました
第57回備後地域連携を考える会を、8月28日に開催いたしました。当日は会場34名、WEB47名の方に参加していただきました。座長を寺岡記念病院 脳神経外科部長 竹信敦充先生に務めていただきました。
藍の都脳神経外科病院 理事長・院長 佐々木庸先生より「脳卒中痙縮を地域で支える取り組みについて~医師の視点~」と題して、ご講演いただきました。
藍の都脳神経外科病院におけるボツリヌス治療の流れ、施注の正確性を向上させるための工夫を話されました。
・施注に超音波を用いることで、正確性が高くなるが、時間を要するので患者の負担が長くなる。
・治療は早期に痙縮を取り、TMS等のデバイスを早めに実施すると効果が上がっている。
脳卒中後の痙縮の治療は多職種が連携して急性期・回復期・慢性期・在宅全てにおいて、1年後を目処に改善を目指す治療を行われているとのことでした。
続いて、藍の都脳神経外科病院 リハビリテーション部科長 君浦隆ノ介氏に「脳卒中痙縮を地域で支える取り組みについて~療法士の視点~」と題して講演を行っていただきました。
・機械を用いたニューロリハビリテーションを積極的に行うことで、在院日数が短めになっている。
・脳卒中後の痙縮は無意識に動かす抑制系の神経がダメージを受けることでおこる。脳卒中による運動麻痺から筋肉を使わない生活に慣れていき、筋短縮・繊維化が起こり、悪化していく。このため、早期介入が重要である。
・脳卒中治療ガイドラインでも毒素療法を行うことがエビデンスも高く、勧められるが、日本ではなかなか進められていない。
・筋紡錘の興奮性が増大する時点から、ボツリヌス治療の実施が検討される。
・MRS・NIHSS、MMSE(認知機能)が落ちている方は痙縮発生が予測される。
・ボツリヌス治療はリハビリ併用が重要である。リハビリに機械を併用することで効果的に進めるようになる。痙縮が強くなるようであれば、装具を治療に用いるのが良い。
講演終了後の質疑応答の中で、「日常の臨床では行き届かない場合があるので、療法士を中心としてチーム治療を行うことは新たな気づきであった。」との感想が寄せられました。
今回の会では、脳卒中後の痙縮に対する医師・療法士双方の視点からの取り組みが紹介され、地域での多職種連携の重要性を再認識する機会となりました。