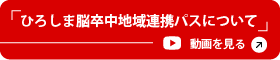第56回備後地域連携を考える会を開催しました
第56回備後地域連携を考える会兼第11回症例検討会を4/11に開催しました。
脳神経センター大田記念病院リハビリ棟3階リハビリテーションセンターにて、岡山ロボケアセンター株式会社、株式会社スペース・バイオ・ラボラトリーズの2社が機器展示を行いました。
引き続き、脳神経センター大田記念病院4階大会議室にて症例検討会を開催しました。
演題:「高次脳機能障害の勘所~高次脳機能評価とその解釈・かかわり方のポイント~」
座長:脳神経センター大田記念病院 脳神経内科部長 寺澤 由佳先生
演者:川崎医療福祉大学 リハビリテーション学部 言語聴覚療 副学科長教授 時田春樹先生
近年、失語症・高次脳機能障害といった「成人言語・認知」が増加していることが言語聴覚士へのアンケートから報告されている。高次脳機能障害は、画像診断技術が必要である、目に見えにくい障害である、環境が変わることで反応の浮動性がある、似たような症状があるので、鑑別が難しい、とのことでした。
大脳の機能について理解すること、高次脳機能検査はWorking Memoryと抑制の機能を良くみている検査を重視することが重要であり、リハビリテーション効果を最大限に出すためには、「うつ」傾向の予防が大切である。また、患者自身が自信を持てるようなリハビリ介入が必要とのことでした。
続いて事例検討会を開催しました。
内容:「事例から学ぶ高次脳機能障害への対応 Q&A」
司会:水永リハビリテーション病院 リハビリテーション部部長 古澤 潤一氏
司会より事例を紹介した後、時田先生にご回答いただいた。
事例1:純粋語聾の患者に対するSLTA以外の確定評価・家族の負担軽減について
純粋語聾については、言語機能だけでなく、患者になじみがある環境音を集めて、評価すると良い。
事例2:生活動作における手順の理解と獲得がうまくいかない場合の評価・訓練について
脳の画像より、臨床所見が重ために出ている。左前頭葉の内側面(運動の出力)の発動性が低下することで、全失語になっているのではないかと思う。