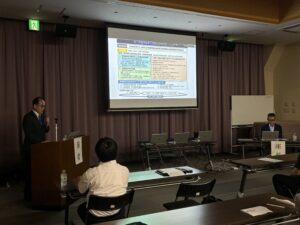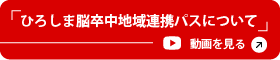第23回備後脳卒中ネットワークシンポジウムを開催しました
第23回備後脳卒中ネットワークシンポジウムを9月3日(水)に脳神経センター大田記念病院で開催しました。会場49名、WEB54名の参加でした。
事業内容:
司会:脳神経センター大田記念病院 地域医療連携室 神本 綾乃氏
報告:「脳卒中地域連携パスについて」
演者:脳神経センター大田記念病院 脳神経内科 寺澤 由佳先生
脳卒中地域連携パスの歴史及び現状と課題を説明していただいた。課題としては、パスデータの活用方法が確立できていないことが挙げられる。
講演:「ひろしま脳卒中地域連携パスの現状と課題について」
演者:広島県健康づくり推進課 課長 武内 聡氏
• 広島県の循環器病対策の現状と目標
• 広島県の循環器病対策の取組
• ひろしま脳卒中地域連携パスデータ分析結果の報告
この結果からは、広島県全体の脳卒中患者の情報が反映されているとは言い難い。急性期と回復期両方のベッドをもつ医療機関において、パス以外の方法で情報連携がされていることが要因と考えられる。
• 生活期の関係者に向けた研修の実施
脳卒中の疾患理解、パスの分析結果の共有を行ったが、アンケート結果の86%からパス自体が届かない、利用の仕方が分からないと回答があった。また、医療パスについての研修を全員が希望した。
これにより、ケアマネジャー向け研修会を2025/11/11にWEB開催する。来年度以降も継続的に勉強会を行うことを検討している。
特別講演:「脳卒中医療のFuture & Past」
座長:NPO法人備後脳卒中ネットワーク 理事長 大田 泰正先生
演者:自治医科大学 内科学講座 神経内科学部門 教授 藤本 茂先生
これからの脳卒中医療は急性期から維持期までの長いスパンで治療及び多職種で患者の支援をしないといけない。
循環型双方性の脳卒中地域連携パスの活用が求められるが、一方向性であることが課題である。患者が急性期医療機関にいる間から相談できる脳卒中相談窓口の設置が求められる。
脳卒中地域連携パスは全国の6割の県で県共通パスを利用している。現状は急性期から回復期病院への流れが主で区間限定となっているが、地域全体で多職種が共有できる情報が入ることが目標である。全国で標準化していくことが大切である。
脳卒中治療の今後は、地域の課題に応じた医療計画・遠隔医療の整備・脳卒中相談窓口の機能向上・脳卒中地域連携パスにおける多職種のニーズの共有が必要である。
パネルディスカッション「地域の看護師連携を考える~退院指導を通してどうつながる・つなげる~」
司会:脳神経センター大田記念病院 地域医療連携室室長 藤井 美穂氏
パネリスト: 福山第一病院 副看護部長 本藤 潤美氏・水永リハビリテーション病院 看護師長 中川 悠氏・福山リハビリテーション病院 看護師長 金丸 修江氏
備後脳卒中ネットワークに参加する、回復期リハビリテーション病棟を有する8施設を対象にアンケートを実施した。
■ 調査の目的
回復期リハビリテーション病棟における脳卒中再発予防指導の現状を把握し、今後の再発予防に向けたより良い連携のあり方を検討する。
■ アンケート結果の概要
すべての施設で「再発予防指導は必要である」と回答があった。一方で、指導を実施できていない理由としては以下の点が挙げられた:
• 患者の重症度が高く、指導が困難である。
• スタッフの人手不足により対応が難しい。
この結果を踏まえ、退院指導のあり方について意見交換を行った。
■ ディスカッションで挙がった主な意見
• 急性期で使用した指導資料を生活期でも活用することで、指導済みの内容が明確になり、継続的な支援につながる。
• 退院時のパス(退院支援計画)が適切に運用されているかが気になる。目標値や掲載項目をより厳選することで、より効果的な退院支援が可能になる。
• 退院指導の内容や処方薬の情報が患者の生活状況に関する情報がより詳しく含まれていると、次の支援につなげやすい。
• 情報提供書に記載されているアレルギー情報などについて、急性期で詳細な情報を取得し、共有できると望ましい。
• 医療機関ではパスに慣れているが、介護施設では見慣れておらず、見づらいとの意見があり、十分に活用されていない可能性がある。
■ 今後の連携に向けた意見交換
参加者からは病院間で相互に見学を行い、現場の取り組みを学び合う機会があると良いとの意見が寄せられた。
藤本先生からは、「地域の課題を共有し、意見交換を行う会議を定期的に開催することが重要。地方都市では規模がまとまりやすく、実施しやすいのではないか」とのご意見をいただいた。
司会者からは、「看護師は病棟にこもりがちになる傾向があるため、今回のような交流の場を今後も積極的に設けていきたい」との意向が示された。