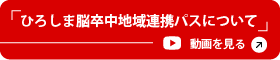第2回医療介護連携の勉強会を開催しました
介護支援専門員を対象とした第2回医療介護連携の勉強会を、6月18日に開催いたしました。当日は27名に参加していただきました。
まり居宅介護支援事業所の岡崎美保氏に司会を務めていただき、水永リハビリテーション病院の古澤潤一氏より「医療介護連携について~令和6年度 医療・介護同時改定を踏まえて~」、脳神経センター大田記念病院の柳生英子氏より「ひろしま脳卒中地域連携パスについて」の講演をいただきました。
古澤氏からは、勉強会開催に至った経緯および令和6年度の診療報酬・介護報酬の同時改定について説明していただき、特にリハビリテーションにおける医療・介護の連携強化の重要性が強調されました。また、社会保障審議会介護給付費分科会の議事録を確認することで、今後の改定に向けて的確な対応が可能であると紹介されました。
課題として、入院中と退院後におけるリハビリ情報の共有不足が挙げられ、医療機関からリハビリテーション実施計画書を受け取ることが運営基準として明文化されました。
介護報酬上の対応としては、通所リハビリおよび介護予防訪問リハビリに「退院時共同指導加算(600単位)」が新設されました。一方で、介護支援専門員には報酬が設定されておらず、業務としての継続が難しいという課題も指摘されています。報酬上のメリットはなくとも、情報共有の観点から介護支援専門員の積極的な参加が期待されます。
また、主治医意見書を作成した医師以外でも居宅サービス計画の作成が可能であり、「顔の見える連携」を通じて、気軽に相談や声かけができる関係づくりの必要性が述べられました。
続いて柳生氏より、「ひろしま脳卒中地域連携パス」についてご説明いただきました。
本パスは、脳卒中患者の発症から生活安定期までの経過を記録するもので、対象は脳卒中に限定されています。
パスは、患者用パスおよび医療関係者向けの「オーバービューパス(急性期・回復期)」で構成されており、自由記載欄には単なる「資料参照」ではなく、見直し可能な具体的な記述を求める方針としています。
また、維持期・生活期から急性期医療機関へ3か月後の情報をフィードバックする仕組みが構築されていますが、現段階では十分に機能していないとされています。
備後脳卒中ネットワークでは、かかりつけ医のみならず介護支援専門員にもパスのコピーを共有する取り組みを進めています。さらに、ホームページ上に記載内容の解説・よくある質問・パスの概要説明などを掲載し、QRコードを貼付することで関係者が容易に内容を確認できる体制を整備しました。脳卒中患者の支援を強化するためには、医療と介護の連携を一層深めることが不可欠であり、介護支援専門員が気軽に相談できるツールの導入や、急変時の情報提供体制の構築が求められています。
また連携パスの活用促進を目的に、研修会や説明会の実施、ホームページの充実を図っており、年2回の症例検討会を通じて運用状況の確認と、幹事会での課題検討・改善活動も行っています。
参加者からは、「ひろしま脳卒中地域連携パスのイメージが具体的になってよかった」「訪問リハビリテーションから、入院医療機関よりリハビリ実施計画書を受け取る重要性について説明を受けた意味がよく理解できた」との感想が寄せられました。